【実質賃金とは?】ニュースでよく聞くけど実際よくわからない人へ、わかりやすく解説!
最近のニュースで「実質賃金が◯ヶ月連続でマイナス」という言葉をよく耳にしませんか?
なんとなく「景気が悪いのかな…」「給料が減ってるってこと?」と思いながらも、実際にはよくわからないままスルーしている方も多いのではないでしょうか。
でも、「実質賃金」はわたしたちの暮らしと密接に関わる、非常に重要なキーワードです。
この記事では、そんな実質賃金について、難しい言葉を使わずに、誰にでもわかるように解説していきます。
そもそも「賃金」って何のこと?
まず前提として、「賃金」とは会社などで働いた人が受け取るお金、つまり 給料 のことです。
そしてこの賃金には2種類あることを知っておくと、話がスッと入ってきます。
名目賃金と実質賃金のちがい
| 種類 | 説明 | たとえ |
|---|---|---|
| 名目賃金 | 実際にもらうお給料の金額(手取りとは別) | 給料として20万円もらっている、など |
| 実質賃金 | 物価の変動を加味して考えた「お金の価値」 | 同じ20万円でも、物価が上がると買える量が減る |
つまり、実質賃金とは、「お金の価値」を物価の変動を踏まえて測ったものなんです。
ここがとても大事なポイントです!
なぜ実質賃金が大事なのか?
給料が上がっても、同時に物価も上がっていたらどうでしょうか?
たとえば、去年より給料が1万円アップしたとしても、物価が2万円分上がっていたら、生活はむしろ苦しくなりますよね。
だからこそ、名目だけではなく「実質」も見ないと、本当に豊かになっているかが分からないのです。
実質賃金の計算方法(ざっくりでOK)
ざっくり言えば、
実質賃金 = 名目賃金 ÷ 物価指数
という計算式になります。
※正確にはもっと細かい指数を使いますが、ここではイメージがつけばOKです。
具体例で考えてみよう
【例1】物価が変わらない場合
- 名目賃金:20万円
- 物価:変わらず(指数1.0)
→ 実質賃金は20万円のまま。変化なし。
【例2】給料アップ、でも物価もアップ
- 名目賃金:21万円(5%アップ)
- 物価:10%アップ(指数1.1)
→ 実質賃金=21万 ÷ 1.1 ≒ 19万0909円
→ 給料は増えたのに、実質的には 損している ことに!
最近の実質賃金はどうなっている?
2022年以降、日本ではエネルギーや食料品などの物価が大きく上がっています。
一方で、給料の上昇がそれに追いつかず、多くの月で実質賃金がマイナスになっています。
実質賃金マイナスとは?
→ 生活が苦しくなっている という意味。
→ 物価が上がりすぎて、給料の価値が下がっている状態。
ニュースで「◯ヶ月連続で実質賃金がマイナス」と言われるのは、まさにこの状況を指しています。
実質賃金が下がるとどうなるの?
私たちの暮らしにこんな影響が出てきます。
- ✔️ 食費・光熱費・日用品の負担が重くなる
- ✔️ 貯金が減る(またはできなくなる)
- ✔️ 外食やレジャーにお金を使わなくなる
- ✔️ 消費が減ると、企業も売上が落ちる
- ✔️ 経済全体が元気を失っていく
つまり、実質賃金が下がることは、個人の生活だけでなく、社会全体の元気にも直結する問題なのです。
なぜ実質賃金が上がらないの?
主な原因としては以下のようなものが挙げられます:
1. 物価の急上昇
世界的な原材料費の高騰や円安などにより、日本の物価は近年急上昇しています。
2. 給料の伸びが遅い
日本は長年、給与の伸びが鈍く、特に中小企業ではなかなか昇給が難しい現状があります。
3. 労働市場の構造的課題
非正規雇用の増加や年功序列賃金の影響で、生産性が上がっても賃金に反映されにくい仕組みが根強く残っています。
私たちにできることは?
「実質賃金が下がる=もうどうしようもない」と感じるかもしれませんが、個人でできる対策もあります。
✔️ 固定費を見直す
通信費、光熱費、保険など、見直すだけで支出が大きく減ることも。
✔️ スキルアップをして収入源を増やす
副業や転職、資格取得なども視野に入れ、「収入を自分で増やす力」を持つことが、長期的には有効です。
✔️ お金の知識を身につける
投資・家計管理・節約術など、「くらしのリテラシー」を高めて、物価変動に負けない生活力を育てましょう。
まとめ
「実質賃金」とは、私たちが受け取るお金の「本当の価値」を示すもの。
名目の金額だけを見て一喜一憂するのではなく、「それで何が買えるのか?」「生活は本当に楽になっているのか?」を考えることが大切です。
これからの時代、物価も働き方もどんどん変わっていきます。
そんな中で、自分の暮らしを守るためにも、「実質賃金」という言葉の意味を知っておくことは、きっと役に立ちます。
💡 この記事は一般的な経済用語の理解を目的としたもので、特定の経済政策や投資判断を推奨するものではありません。
参考リンク
総務省統計局「家計調査」
厚生労働省「毎月勤労統計調査」
日本銀行「物価の安定と経済」

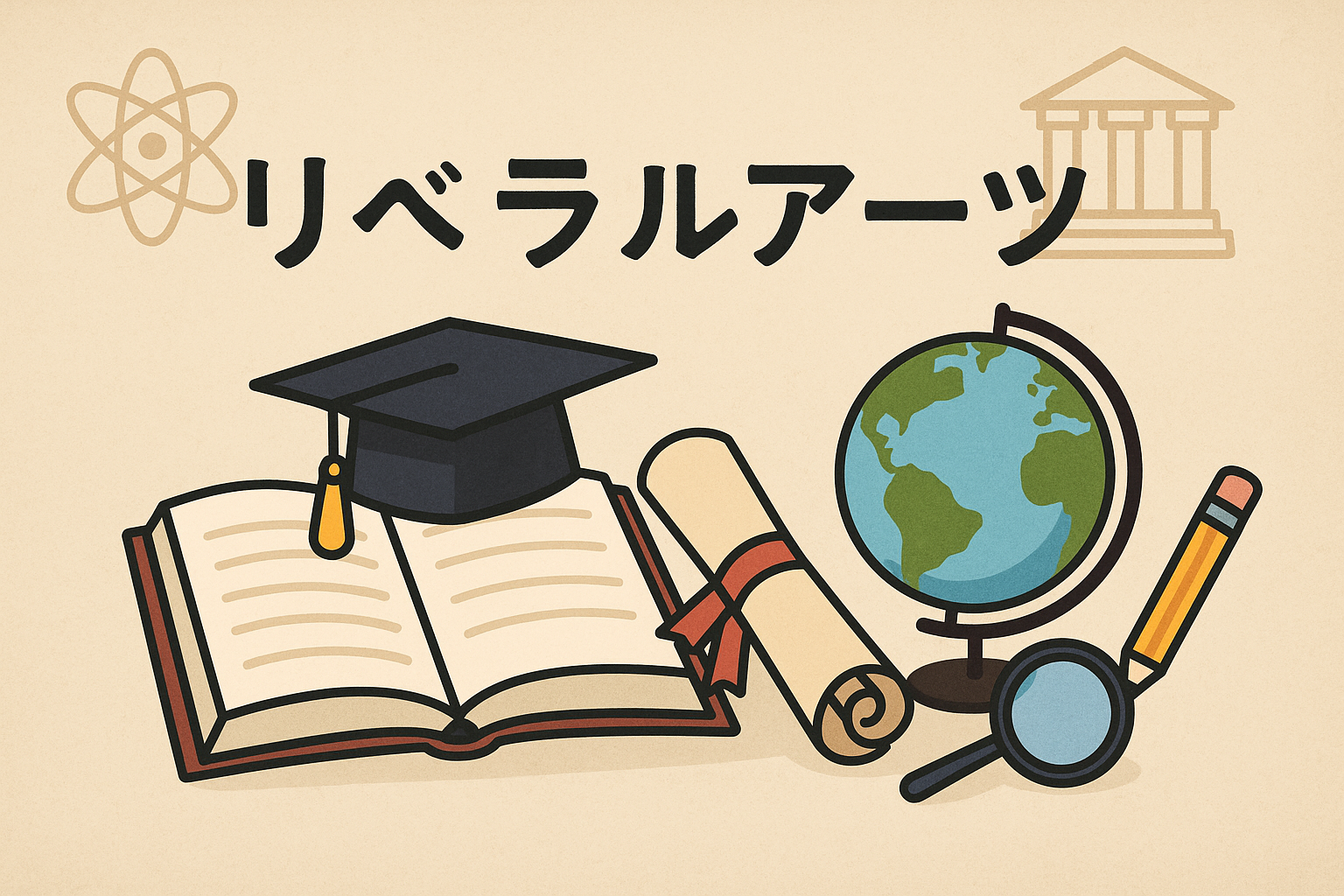

コメント