遺族年金とは?万が一のときに家族を守る制度をわかりやすく解説
人は誰でも、いつか亡くなるものです。
ですがもしも、それが予期せぬタイミングで、自分が家族を残して旅立ってしまったら……。残された家族の生活を守るために、日本には「遺族年金」という制度があります。
遺族年金ってなに?
遺族年金(いぞくねんきん)とは、家計を支えていた人(=被保険者)が亡くなったときに、残された家族が受け取れる年金のことです。
主に2種類あります。
- 遺族基礎年金(いぞくきそねんきん)
- 遺族厚生年金(いぞくこうせいねんきん)
この2つは、どんな人が亡くなったか(自営業か、会社員かなど)によっても違いが出てきます。
誰がもらえるの?
基本的に、亡くなった人に生計を頼っていた家族が対象になります。
具体的には、次のような人たちです。
▼ 遺族基礎年金の対象
- 子どもがいる配偶者(夫または妻)
- 子ども本人(18歳まで/障害がある場合は20歳未満)
※「子ども」とは、亡くなった人の実子・養子を指します。
▼ 遺族厚生年金の対象
- 配偶者(年齢・子どもの有無により条件あり)
- 子ども
- 孫
- 父母
- 祖父母
遺族厚生年金は、対象者の順位が法律で決まっていて、優先順位の高い人から支給されます。
いくらもらえるの?
年金の金額は、人によって異なりますが、大まかな目安は次の通りです。
● 遺族基礎年金
固定金額で、年額 約80万円+子ども加算(2025年度時点)
- 子ども1人 → 約103万円
- 子ども2人 → 約112万円
※加算は2人目までで頭打ちです。
● 遺族厚生年金
亡くなった人の報酬(給料など)に応じて変動します。
- 一般的には、亡くなった人が受け取る予定だった厚生年金の約3/4(子どもがいる場合)など
計算式はやや複雑ですが、月数万円〜十数万円になるケースが多いです。
遺族年金をもらう条件は?
すべての人が遺族年金を受け取れるわけではありません。
次のような条件があります。
▼ 共通の主な条件(抜粋)
- 亡くなった人が、国民年金や厚生年金に一定期間きちんと加入していた
- 保険料を未納で長く放置していない
- 亡くなった当時、家族と生計を同じくしていた
つまり、「ちゃんと年金を納めていた人が突然亡くなった場合」に、その家族を国が支援する、という考え方です。
いつ、どうやって申請するの?
申請は自動では行われません。自分で手続きする必要があります。
▼ 申請先
- 国民年金 → 市区町村の役所の窓口(年金担当)
- 厚生年金 → 年金事務所(日本年金機構)
▼ 手続きに必要な主な書類(例)
- 死亡診断書(または除籍謄本)
- 戸籍謄本
- 住民票
- 年金手帳(基礎年金番号が分かるもの)
- 世帯全員の所得証明 など
必要書類はケースによって変わるので、事前に電話で確認するのがおすすめです。
受け取り方と期間
遺族年金は、申請して認定されると、原則として毎月支給されます(2ヶ月分まとめて)。
また、条件によっては子どもが18歳を超えるタイミングで打ち切られたり、配偶者の再婚などで支給が止まることもあります。
まとめ:遺族年金は「家族を守る」ための公的制度
遺族年金は、「残された家族の生活を守るための最低限のサポート」です。
突然の不幸で収入が途絶えてしまっても、家族が路頭に迷わないよう、国が用意している重要な制度といえます。
ただし、自動的に支給されるわけではなく、自分で手続きをして、必要な書類を揃えることが必要です。
いざという時にあわてないためにも、制度の基本だけでも知っておくことが大切ですね。
参考リンク
- 日本年金機構|遺族年金のご案内
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/

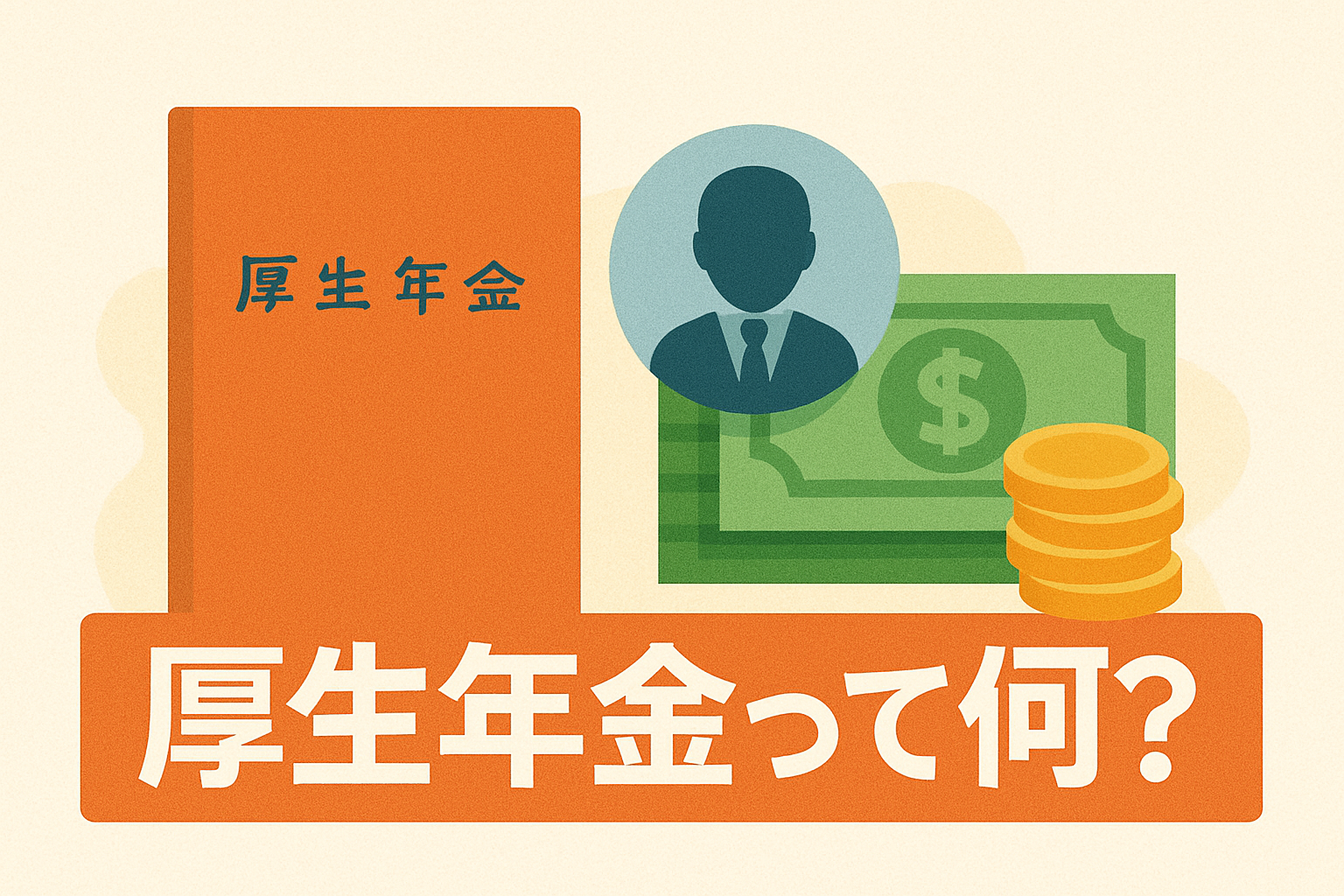
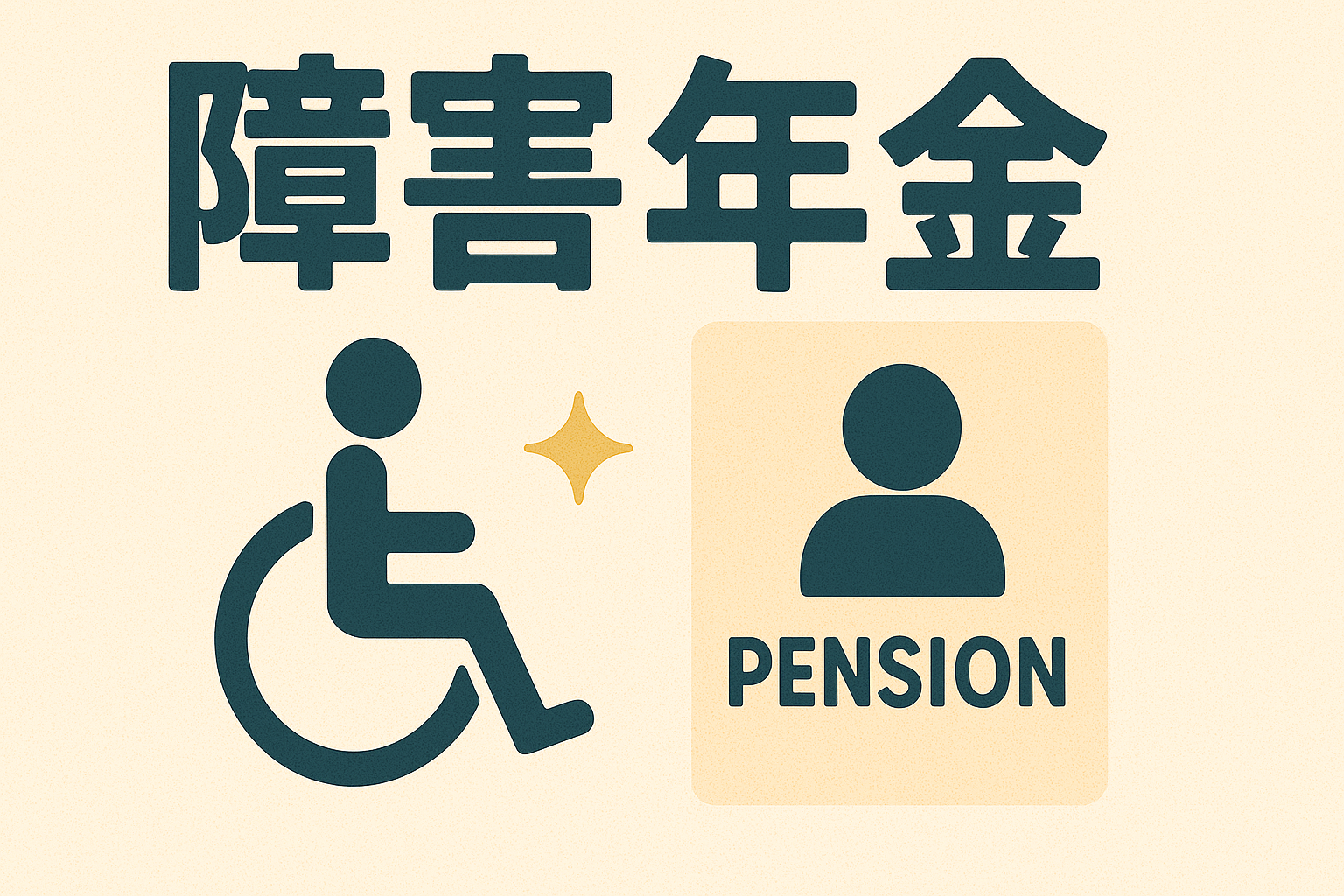
コメント