【障害年金とは?】もしも働けなくなったときの生活を守る制度をやさしく解説
突然の病気やケガで、働けなくなったらどうしよう――。
そんなとき、私たちの生活を支えてくれる「障害年金」という制度があります。
でも、「名前は聞いたことあるけど、なんとなく難しそう」と思っていませんか?
この記事では、障害年金について、できるだけやさしく、誰にでもわかるように解説します。
障害年金とは?
障害年金は、「病気やケガなどで、日常生活や仕事が大きく制限されてしまった人」に対して支給される公的な年金です。
つまり、「障害のために働けない、働きづらい」という人が生活に困らないように支援する目的で作られた制度なんです。
病気やケガの原因は、仕事中の事故だけとは限りません。
日常生活でのけが、交通事故、がん、うつ病、心臓病など、さまざまなケースで受給対象になる可能性があります。
対象となる人は? 誰がもらえるの?
障害年金をもらうには、次の3つの条件を満たしている必要があります。
① 初診日が特定できること
「初診日」とは、最初にその病気やけがで病院を受診した日です。
この日が障害年金の基準になるので、とても大切です。
② 保険料をきちんと納めていること
初診日の前に、原則として直近1年間に保険料を滞納していない、または一定の納付要件を満たしている必要があります。
ただし、20歳未満で発症した場合など、例外もあります。
③ 障害の程度が一定以上であること
障害の程度は、国が定めた基準で「1級」「2級」「3級」などに分けられます。
日常生活がどれくらい制限されているか、仕事ができるかどうかなどが判断基準です。
支給される年金の種類と金額は?
障害年金には、大きく分けて次の2種類があります。
● 障害基礎年金
→ 国民年金に加入している人(主に自営業・学生・主婦など)が対象
→ 1級と2級の人が対象になります
→ 年額の目安(2025年現在):
- 1級:約99万円+子の加算
- 2級:約79万円+子の加算
※たとえば、障害基礎年金2級で子どもが1人いる場合は、約99万円ほどになります。
● 障害厚生年金
→ 厚生年金に加入している人(主に会社員・公務員など)が対象
→ 1級~3級があり、収入に応じて金額が変わります
→ 年額の目安:加入期間や給料の額により異なりますが、障害等級や配偶者・子どもの有無で加算あり
どんな病気・けがが対象になるの?
一部を例にあげると、以下のような病気やけがが障害年金の対象になります。
- 精神疾患(うつ病、統合失調症、双極性障害など)
- 心疾患(心筋梗塞、不整脈など)
- 腎臓病や人工透析が必要な状態
- がん(治療や後遺症で生活に支障が出る場合)
- 脳梗塞・くも膜下出血などの後遺症
- 視覚・聴覚障害
- 交通事故による後遺障害 など
ポイントは、「診断名」よりも、「実際にどれくらい生活や仕事に支障が出ているか」です。
申請の流れ
障害年金の申請は、以下のような流れで進みます。
1. 初診日の確認
まずは、病気やけがで初めて病院にかかった「初診日」を特定します。
2. 書類を集める
- 病歴・就労状況等申立書
- 診断書(主治医に書いてもらいます)
- 年金記録の証明書類(ねんきんネット等で確認)
などを準備します。
3. 年金事務所へ提出
必要書類を整えて、最寄りの年金事務所へ申請します。
4. 審査・結果の通知
申請から2〜3か月ほどで、支給が認められるかどうかの結果が郵送で届きます。
障害年金は「一人で悩まない」が大事
障害年金の申請は、書類も多く、初めての方には少しハードルが高く感じるかもしれません。
でも、年金事務所には相談窓口がありますし、社会保険労務士(社労士)などの専門家に相談することもできます。
「こんな症状じゃ無理かも」と思わず、まずは情報を集めてみましょう。
家族や友人が悩んでいるときにも、こうした制度があることをぜひ教えてあげてください。
まとめ
- 障害年金は、病気やけがで働けなくなった人を支える大切な制度
- 一定の条件を満たせば、精神疾患や内臓疾患など幅広い病気が対象になる
- 申請には書類や手続きが必要だが、年金事務所や専門家に相談できる
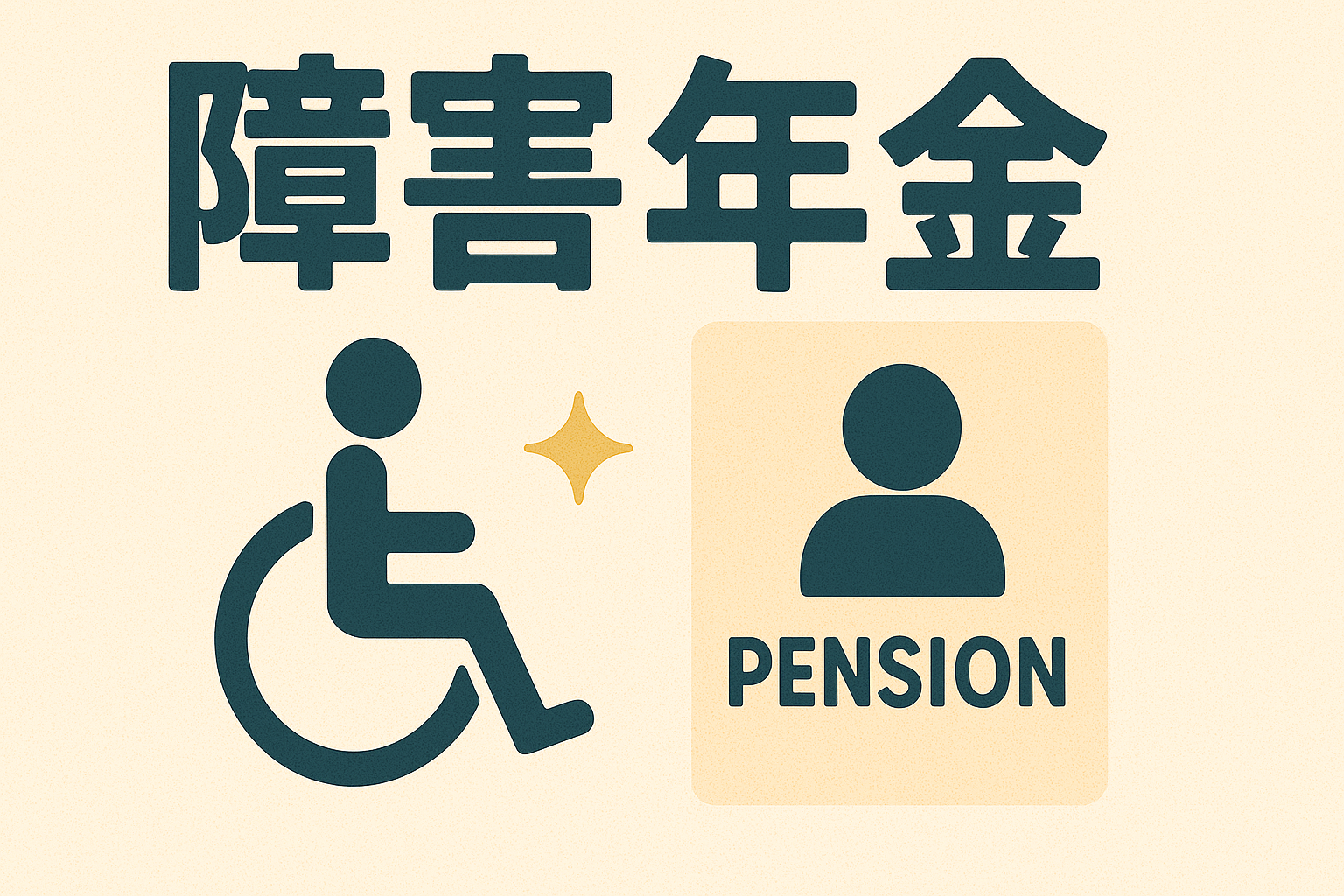

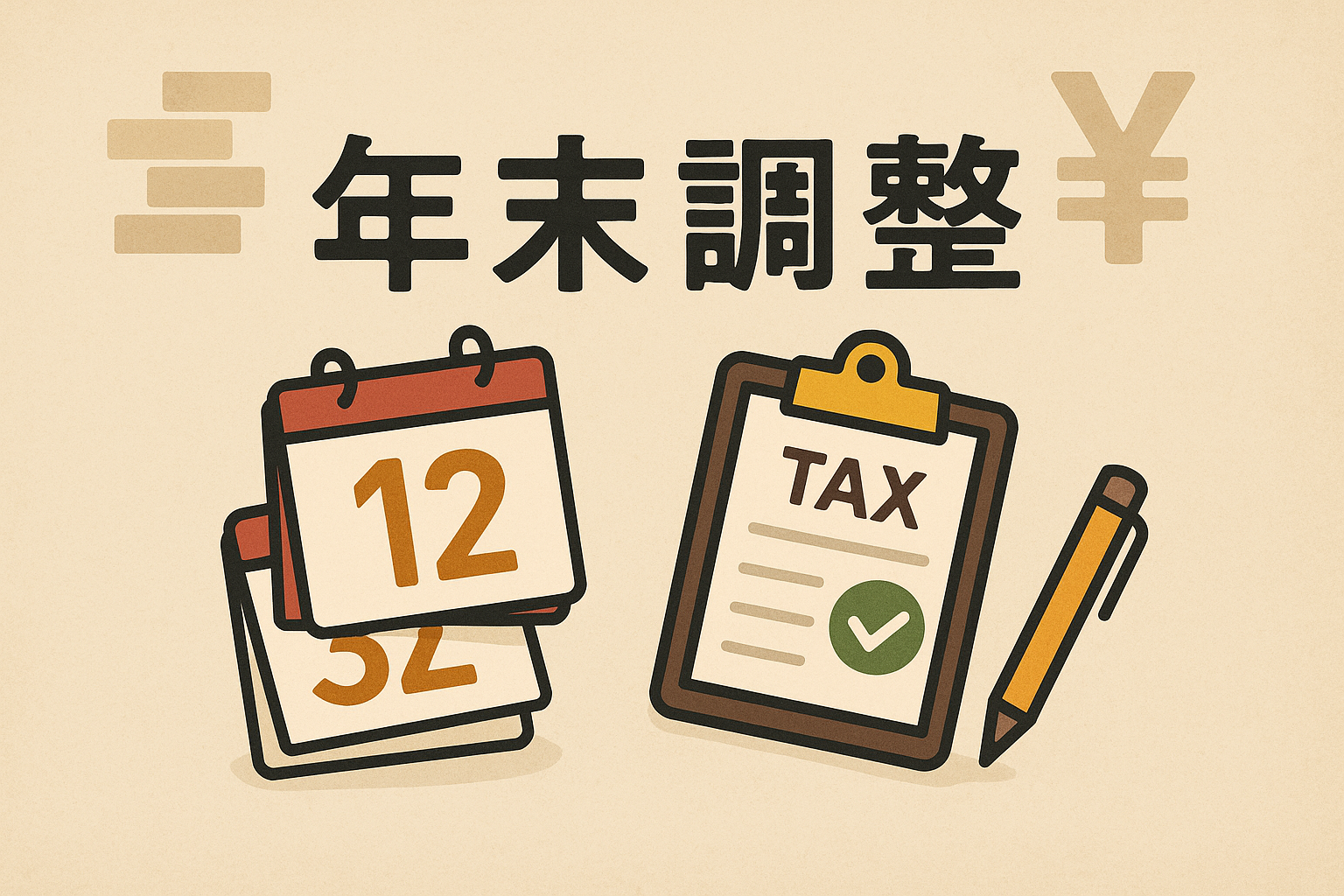
コメント